1.日本への伝来から
明治時代まで
国立劇場編(2008)『日本の伝統芸能講座 音楽』(p.152-169, 414-433)には琵琶の歴史についての詳細な記述がある。それゆえ、ここでは簡単な説明に留める。
日本のリュートの一つである琵琶は、メソポタミアに起源を発する弦楽器である。最古のリュートは動物の皮で覆った共鳴胴を持っていた(ちなみに、今日でも日本のもう一つのリュートである三味線は同じ構造をもつ)。その後、シルクロードを通して文化交流が行われるようになり、次第に全体が木で作られるようになった。アラビア語で木は「ウード」と呼ばれているため、皮のものに対する「木のもの」という意味の「エル・ウード」がヨーロッパでは「リュート」という語になった。

(S.ギニャール コレクション)

この楽器について最も重要な史料となるものは、ササン朝時代(224-651)の銀椀に描かれた文様から知ることができる。ペルシャではこの楽器はバルバット(鴨の胸)と呼ばれていたが、これはアジアにおける名前の影響だと思われる。
この楽器がのちに唐時代(618-907)に中国へ伝わり新しいピパという名で呼ばれるようになったが、おそらくはこのバルバット(鴨の胸)に由来するものと思われる。しかし、ピパの語源には別の説もある。すなわち、撥で弦をはじく二つの重要な動き、すなわち「下から上へ」(ピ)と「上から下へ」(パ)という擬音から来たものとする説である。
日本が7~8世紀に大規模に朝鮮文化や中国文化を受け入れるようになった頃、ピパ(琵琶)も日本へもたらされ、名前も中国語を日本語読みした琵琶(びわ)となった。この琵琶は、今日に至るまで宮廷や社寺で演奏される雅楽で用いられている。唐時代の中国の琵琶のいくつかは、756年に奈良の正倉院が建立されて以降、そこに保存されている。豪華な螺鈿や半貴石の象嵌(ぞうがん)が施されているものや、撥面に西域文化を描いた唐風の絵画がついているものもある。保存されている琵琶は一面を除いて残りはすべて四弦である。
四弦が当時の標準であったことは唯一残る五弦琵琶の撥面に描かれた文様からわかる。これはインドから伝来し聖武天皇(701-756)に献上されたと思われるものであるが、駱駝に乗って四弦琵琶を弾く人が描かれている。このことから、おそらく当時は四弦が普及しており標準であったと私は考える。

今日、宮中の雅楽で演奏されている琵琶は楽琵琶と呼ばれ、細部にわずかな違いが見られるが、奈良の正倉院御物の琵琶とほとんど同じである。楽琵琶は合奏用楽器として、主に主旋律(4分の4拍子と記譜できる)の最強拍をアルペジオで強調する役割を持っている。楽琵琶にも独奏曲の江戸初期に遡る写譜が残るが、演奏技術の伝授は廃れていった。20世紀になって三秘曲の楽譜の復元の試みがいくつかなされているが、実際に雅楽の演奏家の演目に加えられることは稀である(本書の企画者である私は2009年10月20日、スイス、バーゼルにおいてラジオDRS 2で楽琵琶の秘曲の写譜を基にした独奏曲を録音している)。
楽琵琶と平行して、多くは盲目であった琵琶法師によって歌や語り物や読経の伴奏として琵琶が演奏されることもあった。盲人音楽家が雅楽の琵琶を取り入れて活動するようになったのは10世紀末頃からである。
平安時代(794-1185)の宮廷文化は壇ノ浦の戦いで終わりを告げた。平家の盛衰を扱った物語の抜粋には旋律がつけられたが、現存する最古の記録の一つは、琵琶法師の明石覚一(1279-1371)によって書かれた(あるいは編纂された)「覚一本」と呼ばれる『平家物語』の1本である。
平安時代末期ごろには合戦の様子や武将たちの死を語って各地を回った琵琶法師たちがいたが、覚一本の成立は彼らの吟遊の伝統を認めることとなった。平家琵琶という楽器自体は、宮廷で使われる楽琵琶をやや小ぶりに形を変えたものである。しかし音楽ジャンルとしての平家(平家琵琶、平曲)は、日本音楽史における一つの節目を画しており、後世へ大きな影響を与えた。覚一の行ったさまざまな伝統の標準化はその後の琵琶楽の基礎となったばかりでなく、数世紀後に生まれた人形浄瑠璃の義太夫節のような別の語りのジャンルにもその影響が見られるのである。
最も芸術的な平家琵琶に加えて、琵琶法師が経(実際は偽経)を読む際に琵琶の伴奏をつけて、民間の宗教者としても活動したことが琵琶文化のさらなる発展にとって重要なことであった。「琵琶法師」は、字義通りには、「琵琶を弾く僧侶」であるが、その多くは正規の音楽訓練を受けておらず、仏教の知識も少ない人々であった。江戸時代初期に琵琶法師たちは「当道座」という強力で巨大な組織に統合されていった。この組織は琵琶法師たちの活動を統制していたが、社会的に低い地位にある法師たちの生活の保障もしていたのである。しかしながら、九州の琵琶法師たちはこの組織に加わることを拒み、自分たちを「盲僧」という別の呼び名で呼んでいた。

九州、とりわけ薩摩地方は、現代の琵琶楽の発展におおいに寄与している。薩摩地方は、江戸時代(1603-1867)は外部の人が近づくのが困難であった。そのため、この地域独自の文化が発展し、使われていた言葉も都や他の地方のそれとはまったく異なるものであった。
琵琶の世界においても同様であった。薩摩の人々は独自の道を歩み、それぞれの地方でまったく新しいジャンルを発展させていった。読経の際の伴奏だけでは経済的に成り立たなかったため、盲僧琵琶の奏者たちは世俗的な歌も語ることとなった。彼らは当道座に属していなかったために、そうした音楽に三味線の伴奏をつけることが許されていなかった。そのため、17世紀末に、平家琵琶を改変した楽器を用い始めたが、この伝統から今日の薩摩琵琶が生まれたのである。
薩摩琵琶において柱は4個しかなくしかも高さがあるため、演奏の際、弦を柱と柱の間で強く押さえ込まないとどの音程もほとんど出すことができない。繊細な耳と強い力が必要である。大きな扇型の撥を持ったとき、初心者なら手が痛く感じられるほどである。この楽器がもっぱら男性によって演奏されたのも無理はない。
明治時代(1868-1912)になって、薩摩出身者が東京に出て明治政府の中枢で活躍するようになった。それとともに、薩摩琵琶の重要な音楽的特徴は、即興の弾奏を評価する姿勢である。それ以前の薩摩琵琶の詳細については知り得ないため、明らかなのは19世紀に進化した楽器だということである。
明治時代の初頭、明治新政府の政治家の多くはかつて隔絶されていたこの地方の出身であった。薩摩琵琶は近代日本文化のなかで重要な位置を占めており、この楽器への人々の愛着は熱狂的ともいえるほど強いものであった。すでに述べたように薩摩琵琶は「男性的な」特徴をもつため、明治以降の「富国強兵」政策をとって西洋の植民地主義に追随した時代には、とくに重用された。戦場に赴く際もこの楽器を背負っていった兵士がいたと言われている(『西郷隆盛』45~50行目参照)。鹿児島を後にして東京へと向かった政治家たちも携えて行ったのである。
新しく日本の中心となった東京からこの楽器とその音楽は急速に広がり、多くの新しい薩摩琵琶の流派を生んだが、中で最も重要なのは錦心流である。


2.筑前琵琶の歴史

薩摩琵琶の人気が全国に広がり始めたころ、何百年と続く琵琶法師(盲僧)の伝統から脱して新しい現代的なジャンルの創出を目的とした動きが九州北部で起こった。薩摩地方と同様、北九州においても盲僧たちの楽器に決まった形はなかった。あえて一つ挙げるとするなら、いわゆる笹琵琶(笹の葉を模した形※左の写真参照)があるが、それは、三味線を模して、極端なまでに細く軽く持ち運びしやすいものであった。それは主に、盲僧が檀家回りをして、荒神払いを行う際の伴奏用として用いられたのである。
盲僧たちはそうした宗教的な行事を終えた後、娯楽のための琵琶歌も歌った。しかし、幕末に社会が大きく変化するとともに、これは「滑稽琵琶」とよばれる世俗的でひどく低俗なものへと堕落していったのである。

1987年にS.ギニャールが福岡へ現地調査に行った際、若い頃この種のあらゆるおかしな演奏をしてきた大塚源三郎という名の琵琶奏者を訪ねたことがある。彼は楽器を頭上に高く掲げ、色っぽく下卑た詞章を歌ってくれた。「琵琶法師」の堕落についての似たような話を今は亡き薩摩琵琶奏者である普門義則氏から聞いたこともある。
盲僧によって娯楽文化に成り下がってしまった危機をきっかけに、琵琶の歴史は一つの転換点を迎えた。玄清法印(765-823)を祖とし、1200年以上の歴史をもつ名家と称する橘家は、幕末の博多地方の盲僧支配役を務める家柄だった。しかし明治4年に盲僧座が廃止され、宗教活動が認められなくなったために、玄清法印の子孫である橘智定(1848-1919)が、楽器を一つの型に標準化し、のちに筑前琵琶と呼ばれるようになる新しい芸能のジャンルを切り開こうと考えた。筑前地方を発祥とするこのジャンルでもって、薩摩琵琶と対抗しようとしたのである。

智定は、器楽演奏者を集めて演奏活動を行っていたが、そのなかに福岡の別の盲僧の末裔である鶴崎賢定がいた。その後、福岡の歓楽街で三味線を弾いていた吉田竹子が、琵琶を智定に師事するようになった(彼女はのちに独立し東京で琵琶の演奏会を開くまでになっている)。
新しい流派に女性の三味線弾きが加わったということに大きな意味がある。というのは楽琵琶や平家琵琶あるいは薩摩琵琶のいずれも、演奏するのはつねに男性だったからである。日本の芸能の守護神が琵琶を弾く弁財天という女神であるのに、少々不思議ではあるが。
初期の筑前琵琶は調弦だけでなく一定の演奏技術も三味線の奏法から発したものであることは明らかである。事実、筑前琵琶の撥は三味線の撥を模したものであった。智定自身も三味線の名手であったと言われるが、この新しいジャンルの音楽的な要素には、多かれ少なかれ吉田竹子の影響があったことと私は思う。いずれにしろ、薩摩琵琶が勇壮で「男性的」と言われるのに対し、筑前琵琶が優美で女性的であるのには、三味線の影響が認められるのである。
橘智定は、鹿児島で現地調査をし、薩摩盲僧琵琶から派生しその独特な芸術的特性を受け継ぐ薩摩琵琶を、彼の音楽の基礎とした。筑前琵琶の合いの手の型のいくつかには今なお薩摩琵琶の即興演奏の名残がはっきりと見て取れる。
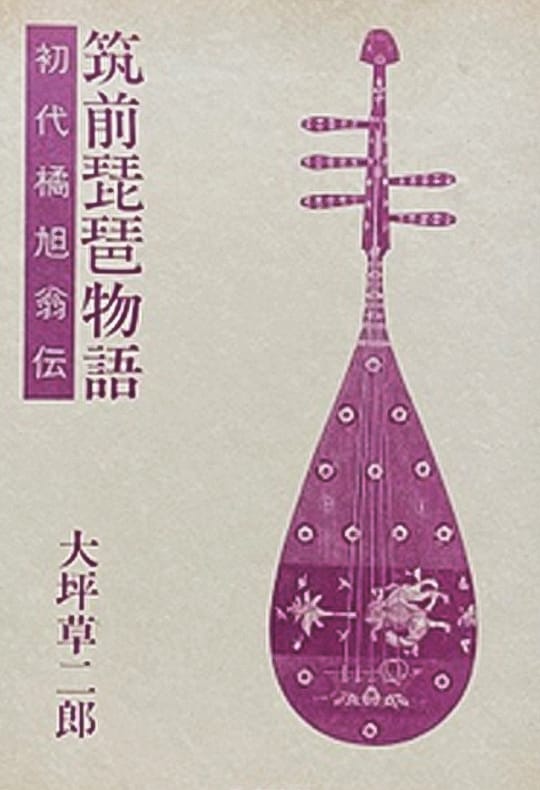
1896年に橘智定は東京に出て旭翁という雅号で演奏したが、それ以降、彼は旭翁の名で知られるようになった。そして、「橘流旭会」という流派を立ち上げ初代旭翁となった。この会は、2年後に「大日本旭会」と改称する。今日でもこの流派の会員はみな、姓の後、一字目に旭の漢字のついた雅号を所属の証として持っている。この雅号は演奏の際は常に名字とともに用いられる。
初期の筑前琵琶は、四弦楽器であった。これは今日ではめったに演奏されることがない。控えめなサイズの四弦筑前琵琶は、北九州地方の盲僧が数世紀にわたって弾いていた楽器を基にしたものと思われる。
やがて初代旭翁は楽器改良の実験を始めた。彼は、四弦の筑前琵琶の調弦(B,e,b,b)と薩摩琵琶の調弦(e,B,e,f#)とを組み合わせた調弦(e, B, e, f#, b)の五弦琵琶を創り出し、1910年に特許をとった。この発明によって弾奏のスタイルが豊かになったばかりでなく、新しい芸術への評価も高まったのである。智定はおそらく既に述べた奈良・正倉院の御物に匹敵するほど風格のある五弦琵琶を創るという夢を持っていたにちがいない。このことが大坪草二郎(1983)『筑前琵琶物語』の表紙に正倉院御物の五弦琵琶が描かれている理由なのであろう。
今日の標準である五弦筑前琵琶は初代旭翁と彼の次男の手によって完成された。次男も琵琶の演奏家で父親の演奏旅行に同伴しており、芸術的にも相性がよかった。彼にはやはり琵琶演奏家である兄がいたが、初代旭翁が長男を演奏旅行に伴うことはなかった。
長男は、西洋音楽の摂取なども試み、進取の気性に富んでいたが、次男はレベルの高い芸術を目指す伝統主義者であった。こうした彼の芸術志向の高い才能の点から、父はつねに次男に目をかけており、晩年には次男が父の芸術遺産を忠実に受け継いでくれる独自の会を創設することを認めていた。それゆえ長男は、初代旭翁が1919年に死去したのち、長男が父の後を継ぐという当時の慣習から、橘旭翁二世の名を襲名し「大日本旭会」(以下「旭会」と略。現在では「筑前琵琶日本旭会」)を継承して、その家元に就任した。一方、次男は初代橘旭宗(1892-1971)を名乗り、あらたに「筑前琵琶 日本橘会(以下「橘会」と略)」を立ち上げてその家元となったのである。

旭会と橘会は今日でもなお筑前琵琶の二つの重要な流派である。20世紀初頭に琵琶の演奏が大流行したおりには、このほかにも多くの流派や会の誕生を見たが、今日ではほとんど残っていない。
初代橘旭宗は琵琶というジャンルを全国的に広げるため、当初、主に東京に活動拠点を置いていた。しかし1923年に関東大震災が起こって後しばらくの間、大阪に移住し、大阪で会の運営を行い、奏法を指導していた。このことは、大阪に住んでいた17歳の山崎旭萃(1906-2006)が家元から直接指導を受ける絶好の機会であった。
初代橘旭宗は指導資格のある「教授」より上の資格伝位者にのみ指導をしており、山崎旭萃は当時「教授」資格の4段下という立場だった。旭萃が初代旭宗から直接稽古をつけてもらえた理由は、初代旭宗が彼女の卓越した技術と歌唱の技能をただちに見抜き、琵琶奏者としての将来性があると高い期待を抱いたからである。

山崎旭萃は、撥で叩かれるのが珍しくないような辛い稽古をしたことを覚えている。それでもその稽古に耐え、次第に宗匠のお気に入りの弟子になった。そして、初代旭宗の厳しい稽古は成果をもたらした。彼は高い技術が必要な曲、たとえば『茨木』を作曲したが、とりわけ山崎旭萃の特殊な声質を最大限生かせるよう配慮したのである。彼は旭萃に、父旭翁から受け継いだ理想にしたがって、筑前琵琶の歌唱法や演奏法はいかにあるべきかを、非常に厳しく伝授した。山崎はそれを真摯に受け止め創始者の残した遺産を継ぐために能力の限りを尽くしたのである。残念なのは、初代旭宗は、自分に厳しく、要求が非常に高い人であったため、自身の演奏や歌唱を録音することを許さなかったことである。初代の演奏が実際はどのようなものだったのか、橘会の会員には具体的なことはわからないままである。
山崎旭萃の正統的演奏スタイルの追求は、記譜法を重視することに反映されている。橘会の楽譜は、その正確さや明瞭性、洗練度などにおいて旭会のそれとは異なる。旭会では細かい点の多くは演奏者の自由に任されるのである。それ故、楽譜は単なる演奏の手がかりに過ぎない。それに対して、橘会にはまさに西洋音楽で言う「原典Urtext」ともいえるものがあり、この「原典」に忠実に従っているために、初代旭宗の作品の高い芸術性の再現が可能となり、二人の「人間国宝」を生み出したのだといえる。日本の伝統芸能の世界において口伝も重要ではあるが、曖昧でなく明確に規定されたスタイルがあってこそ、芸術は道を間違えることがないと私は考える。演奏者たちの実践において世代から世代へと伝承され深みを帯びていくのである。
3.橘会における筑前琵琶の現状
橘会の家元は、初代橘旭宗の息子である橘旭宗二世であり、会で最も権威ある存在であるが、現時点では高齢になられたため、公的には二世の長女の橘旭帝(次期家元)が実務を執っている。
橘旭宗二世も旭帝も、どちらも琵琶演奏を職業とはしていない。それゆえ旭宗二世は、音楽に関する一切を山崎旭萃に任せて、特に山崎が宗範という称号を用いることを認許したが、宗範という称号は、山崎旭萃の死去後空席となっている。現在では、山崎が最も信頼していた弟子の奥村旭翠が芸術における主導権を握っている。そして奥村もまた「人間国宝」に選ばれている。
奥村は山崎に師事してすべての演目を学び自分のものとし、橘会においてこれらの曲を伝授することができる唯一の人である。
2020年12月末現在、橘会は全国に258名の会員を擁しており、その多くは関西と関東、そして主に福岡や鹿児島に在住している。奥村は大阪、京都、奈良、滋賀および広島に弟子を抱えて指導している。東京、名古屋や別の地域に住む会員はわずかである。
日本の伝統芸術の慣習として流派にはピラミッド状の位階(伝位)がある。現在そのトップは宗範(かつては山崎旭萃が保有)と総師範があるが現在空席である。次が大師範であり奥村旭翠ともう一人がそれにあたる。次のランクは秀師範で5人いるが本書の企画者である私もその一人である。さらにその下に40人の師範がいる。門弟は、一定のレベルに達し、かなりの曲数を習得し、試験に合格すれば師範になることができる。その下には別の10の伝位があり、門弟は才能や稽古の程度により少なくとも1~3年ごとに昇伝することができる。

日本のあらゆる伝統芸能や芸術分野におけると同様、門弟は家元が認許した伝位免状を受ける際、一定額を支払わなければならない。橘会会員として年会費も必要であるが、会員となると季刊の会報誌を受け取ることができる。そしてたいていの場合月謝を払って師匠から稽古をつけてもらう。琵琶を展示して売る店がないため、楽器や撥はたいてい師匠から購入するか、わずかに残っている琵琶工房から直接購入することになる(楽器購入の方法はインターネットの発展とともに変わってきている)。
詞章の書かれた教本や弾奏法に関する本、あるいはさまざまな筑前琵琶の弾奏の合いの手の弾法譜を購入できるのは、橘会会員のみである。原則としてコピーすることは禁じられている。それゆえ本書でも、1冊に
5~7曲ずつの楽譜を収めた15冊の原本に対してコピーの許可は下りていない。
筑前琵琶のような伝統的ジャンルには、それ自体、心身を鍛練し、知識と意識を高める訓練としての一種の教訓的意味がある。目標は舞台に立って生計を立てる芸術家になることではない。よい演奏者は教師になるのであって、職業的演奏家になるのではない。しかし、たとえ舞台に立てたとしても、演奏者はそのことを賞賛されはするが、鍛錬と稽古という基本概念は変わることがない。
会員による演奏会は、数時間続くこともある。20人以上の演奏者が舞台に立って、これまで稽古してきた曲を15分程度に短縮した抜粋を演奏するのである。初心者はこうした演奏会の初めのほうに出演し、その後、技術と伝位の高いものへと続く。演奏会の最後にはその会で最も伝位の高い人が演奏して、会は最高潮に達する。
演奏披露のための最大で最も重要なのが全国演奏大会で、持ち回りで日本各地の都市で行われる。多くの人がこの全国演奏大会への参加を希望するため、全員が出演することができるよう数人で1つの曲を合奏することもある。
こうした演奏会すべてに共通するのは、参加者が出演権を得るために一定の金額を支払うが、チケットは市販されず一般観客に無料で公開されているということである。演奏会形式の会は、一方では橘会の存在証明であり、他方では門弟の稽古を披露する場でもあるためである。全国演奏大会は、かつては大きな社交の場でもあった。演奏会の翌日にはつねに観光旅行が組まれていた。しかし、近年は、出演者の多くが大会当日に帰宅することを望むようになったため、後に演奏会後はパーティが開かれるだけとなった。
第二次世界大戦以前の初代旭宗の頃には会員の数は海外を含めて8300人にのぼっていたが、戦後状況は大きく変化した。日本の敗戦は戦記物への興味を失わせた。しかし、現在では、高年齢層の趣味としての琵琶演奏というイメージは数十年前ほど強くなくなっている。若い人々も音楽を愛し、伝統的な稽古に関心をもつようになり、英雄や戦記物を語る琵琶楽に入ることに、もはやためらいを持たなくなっている。琵琶は1995年に「重要無形文化財」に指定されており、若い人々の日本文化や伝統芸能に対する関心は以前より以上に高まっているようだ。これは橘会会員にはもちろんのこと、日本の琵琶界全体にとって喜ばしい傾向であり、琵琶という魅力的な芸術の将来が明るいことの証明でもある。
参考文献
岸辺成雄他編(1981~1983)『音楽大事典』1~6巻、平凡社
平野健次、上参郷祐康、蒲生郷昭監修(1989)『日本音楽大事典』平凡社
国立劇場編、小島美子監修(2008)『日本の伝統芸能講座 音楽』淡交社
武蔵野音楽大学楽器博物館編(2003、2011改訂)「武蔵野音楽大学楽器博物館研究報告書 Ⅸ」


