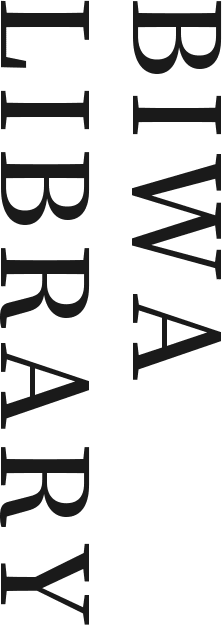-
太 閤 逝 きて蓋世 の -
雄 図 はいづこ大阪城 - 忠臣義士はありながら
-
小 人 内にはびこりて - 今は徳川家康の
-
其の
術 中 に陥 れる -
家運の末を
如何 にせん -
さても
豊臣 徳川の - 和議は再び破れしかば
- 関東勢は諸道より
-
攻め寄せ
来 ると聞えけり -
爰 に豊臣 右大臣秀頼の臣 -
木村
長門守 重成は -
こたびは
大 御所家康の - 首を我手にあげざれば
-
生きて再び
還 らじと -
覚悟定めて
今 生 の -
名残 に妻の白菊と -
別れの
杯 酌 み交 し -
やがて
鼓 を調 べつゝ -
謡 ふや須磨の一曲に -
難波 の葦 の短夜 も -
更 くるを知らぬ風 情 なり -
白菊
齢 は若けれど -
さすが
健 気 の心より -
夫 の身の上憂 ひつゝ -
此の
期 に臨 み悠々と - 遊び楽しみ給ふこそ
-
いとも
本 意 なくおもほゆれ -
わけて
今朝 よりは一 粒 の -
御 食事さへ召し給はず -
若 しも此 まゝ戦場に - 出でさせ給ふことならば
-
日頃の勇気も
鈍 らせて -
思ひのまゝの
御 働 きも -
如何 あらんとかひがひしく -
真心 こめてぞ諌 めける -
重成
容 を改めて - そもじ聞かずや其の昔
-
八幡 太郎の御 内 にて -
末割 四郎といへる武 者 -
敵に
喉 を射 通 され -
其の
傷口 より飯 吐 き出 で -
醜 き最期 を遂げしとぞ -
斯 る恥辱 を後 の世に -
残さんことを気
遣 ひて - 吾は食事を取らぬぞと
- 云へる言葉に白菊は
-
実 にも夫 のいさぎよき - 覚悟の程を今さらに
-
悟 りて深く感じ入り -
何 気 なき様装 ひて - ふと其席を立去りぬ
-
斯 りし程に出陣の - 時刻迫れば重成は
-
二度 三度白菊を - 呼べど答のあらざれば
- 常の居間へと行き見るに
- こはそも如何に何事ぞ
-
懐 剣 喉 を貫 きて
-
朱 に染りて打伏せり - 重成驚き抱き上ぐれば
- 早玉の緒も絶え果てゝ
-
施 す術 もなかりけり -
傍 を見れば一封 の遺書 -
取る手
遅 しと読み下 せば -
一足 先に死出の山 -
越えて
冥 土 に待たんとの -
いと
麗 はしき筆の跡 -
殊 勝 の覚悟に重成は -
暫時 瞑目 合 掌 し -
やがて
門 出 の準備 を整 へ - いざと兜を手に取れば
-
中 より薫 る名 香 は -
今はの
際 に白菊が -
心と共に
焚 き籠 めし - 其のたしなみと知られけり
- 今は勇気も百倍し
-
逸 りにはやる若駒に -
打ち
跨 りて出陣す -
晨鶏 再ビ鳴イテ残月薄 ク -
征馬
連 リニ嘶 イテ行 人 出 ヅ -
時しも
元 和 元年の -
五月
六日 の東雲 も - 早ほのぼのと明け渡る
-
空に
靡 くや旗指物 - 近づく敵の軍勢は
-
関東一の
剛 の者 -
井伊
直 孝 が率 いたる - 一万余騎とぞ知られける
- あな物々しやと重成は
-
二千余騎にて
駆 け向ひ -
矢庭に駒を
躍 らせて - 敵陣深く突いて入る
-
槍の穂先は
電光 の -
空に
閃 く如 くにて -
如何なる天魔
鬼神 も - 敵せんやうぞなかりける
-
斯 る所に敵の猛将 -
庵原 助右 エ 門 馳せ来り -
槍 打扱 き突きかゝるを -
重成
動 ぜず渡り合ひ -
龍 虎 の争ふ如くにて -
暫し
劇 しく戦ひけり -
さしも
手 垂 の重成も -
数 ヶ所の深手身に負ひて -
心は
弥 猛 に逸 れども -
進退遂に
谷 まりて -
あはれ二十二歳を一
期 とし -
難波 の葦 に置く露の - 玉と散りしぞ勇ましき
-
伽 羅 焚き籠めし其の兜 - 忍びの緒さへ切り捨てゝ
-
命
縮 めし益 良雄 や -
首
実検 の晴 の場 に - 敵の大将家康も
-
あっぱれ武士の
鑑 ぞと -
称 へし誉は難波津 の -
咲く花よりも
芳 しく -
万代 かけて匂ふらん
-
1.-7.
豊臣秀吉既に亡く
その志もむなしい大阪城
忠義の家来はいるものの
悪人たちもはびこって
今は徳川家康の
罠にはまって豊臣家
そのゆく末はどうなるか -
8.-11.
さて豊臣と徳川の
和議は再び破られた
関東勢は四方から
攻め寄せてくるとの知らせ -
12.-23.
ここに豊臣秀頼の
忠臣木村重成は
今度は大御所家康の
首をこの手であげぬうちは
生きて再び帰るまいと
覚悟を決めてこの世の名残
妻白菊と酒を飲み
やがて鼓を打ちながら
須磨の一曲謡ううち
短い夜も更けてゆく -
24.-37.
白菊は若くけなげもの
夫のことを心配し
「これからいくさという時に
優雅に遊んでいらっしゃる
よろしくないと存じます
しかも今朝からひとつぶも
食事を取っておられません
このまま出陣されたのでは
立派な働きできません
いかがなものでありましょう」と
真心こめていましめる -
38.-47.
重成はあらたまり
「そなたも聞いたことがあろう
かつて八幡太郎の家来
末割四郎という武者が
いくさで喉を敵に射られ
食った飯をそこから吐いて
醜い死にざまだったそうな
そんな恥をかかないために
わたしは食事をしないのだ」と -
48.-53.
言った言葉に白菊は
夫のいさぎよい覚悟
今さらながら感じ入り
何げない様子のままで
ふっとその場を立ち去った -
54.-58.
やがてそのうち出陣の
時が来たので重成は
二度三度と白菊を
呼んでも返事をしないため
普段の居間に行ってみると -
59.-64.
これは一体どうしたこと
懐剣で喉を突き通し
真っ赤に染まって倒れている
驚き抱き上げてみたものの
既に命は尽きていて
どうすることもできはせぬ
-
65.-69.
あたりを見ると書き置き一通
急いで取って読んでみる
「一足お先に死出の山
超えてあの世で待ってます」
美しい字で書いてある -
70.-77.
殊勝な覚悟に重成は
しばらく目を閉じ手を合わせ
そして門出の仕度を整え
いざと兜を手に取れば
その中からはよいかおり
これこそ最期に白菊が
心をこめて焚いた香
そのたしなみを示すもの -
78.-82.
重成は勇気をふるい
馬にまたがり出陣する
夜明けを告げる鶏に
うっすら空に残る月
軍馬しきりにいなないて
人は戦地へ歩み出す -
83.-90.
時に元和元年の
五月六日の朝早く
空もほのぼの明けてゆく
旗指物をなびかせて
近づく敵の軍勢は
関東一と名も高い
井伊直孝の一万騎 -
91.-98.
「ああ大げさな」と重成は
二千騎ひきいて立ち向かい
馬を駆けさせ敵陣に
突き入れたその槍先は
あたかも電光ひらめくよう
いかなる鬼であろうとも
到底かないそうにない -
99.-104.
そこに走ってやってきた
敵将庵原助右衛門
槍をしごいて突きかかる
重成あわてず相手となり
竜虎の争う激しさで
しばらく戦い続けたが -
105.-111.
さすがに強い重成も
いくつも負った深い傷
いくら心がはやっても
ついに身動きかなわずに
二十二歳の一生を
難波に散らす勇ましさ -
112.-120.
伽羅の香かおるその兜
忍びの緒さえ切っておく
決死の覚悟の美丈夫に
首実検の場に臨む
敵の大将家康も
あっぱれ武士の鑑だと
褒めたたえたその名誉
難波の花よりかんばしく
いつの世までも匂うだろう