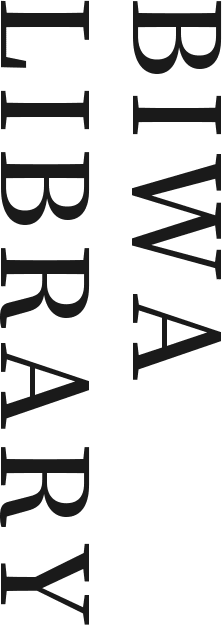- 祇園精舎の鐘の声
-
諸行無常の
響 あり - 沙羅双樹の花の色
-
盛者必衰の
理 を表す - 九重の雲井にまがう花がすみ
- 京の都をわが世とぞ
-
栄華の美酒に
酔 ひ痴 れて -
巫山 の夢にうたゝ寝の -
驕 る六波羅平家の一門 -
折しもあれや
暁 の -
枕をゆする
鬨 の声 -
雷 の如くに響くなり -
これぞ
右兵エ佐 源の頼朝 が -
笹
竜胆 の紋そめて -
掲 ぐる白旗 星月 夜 - 鎌倉山におし立てゝ
-
軍馬
嘶 き兵勇み - 雪崩を打って攻め上る
-
富士川
辺 の水鳥 の - 羽音に浮き立つ赤旗は
- 風に飛び散り影もなし
- くりから峠の火牛の計
-
北の
守 りは潰 え果て - 木曽源氏の大軍は
- 潮をなして迫りよせ
-
逢坂山に
駒 を立つ - かっては平氏に非ずんば
- 人に非ずと豪語せる
-
花の都の平家の
公達 -
今はたゞ
六 波羅〔館〕に火を放ち - 炎と花を背に浴びて
- 二度と帰らぬ死出の旅
- 都をすてゝ西海え
-
逃れ
走 るも運命 なり - こゝに清盛公の御舎弟にて
-
薩摩の守
忠度 公は - 供の数騎をしたがへて
-
淀の川辺の
宵闇 に - まぎれて都に引き返し
-
ひそと
訪 ぬるその先は -
三 位 藤 原 俊 成 卿 の -
五条の
館 とおぼえたり -
忠度公は
三位 の前 に歩みより -
世 静まり候 はば -
勅撰歌集の
御定 下ると承 る -
我が生涯の
面目 に -
一首なりとも
先生 の - 御恩を受くれば幸にて候と
- 鎧の引き合せより
- 巻物一つ取り出だし
-
捧 ぐる御 手 に散る涙 - 三位の卿はそれをきゝ
-
さるべき時の
来 りなば -
必ず御意に
副 ひ申すべしと - 答へければ
- 忠度公はよろこびて
- 今は西海の波に沈まば沈め
-
山野に
屍 をさらすとも -
思 い置く事更 になしと -
西を指して
進 みつゝ -
前途は程
遠 し思ひを -
雁山 の夕 べの雲 にはす -
と口ずさめば
俊成 卿は -
涙を
流 して見送り給う -
さゞ波や志賀の
都 は荒れにしを - 昔ながらの山ざくらかな
-
実 に麗 はしき歌の道 -
身はたとへ滅びの道を
歩 むとも -
歌に託する
武士 の -
心は志賀の
湖 に映え - 遺せし人のゆかしさを
-
永久 に伝へて香るらん - 永久に伝へて香るらん
-
1.-4.
祇園精舎のその鐘は
諸行無常と鳴り響く
沙羅双樹の花の色
人はかならず衰える
世のことわりを教えてくれる -
5.-9.
雲にも見える花ざかり
京の都でわがもの顔
酒に酔い女とたわむれ
驕りたかぶる平家の一門 -
10.-12.
しかしその時夜が明けて
眠りをさます鬨の声
雷のように響きわたる -
13.-18.
これこそ源頼朝が
笹竜胆の紋を染め
掲げた源氏の白旗を
鎌倉山におし立てて
馬はいななき人は勇み
雪崩をうって攻めのぼる -
19.-26.
富士川では水鳥の
羽音におどろき浮き足立ち
平家の赤旗あとかたもない
くりから峠では火牛の計
北に向かった平家軍を
うち破った木曽軍は
怒濤のように都に迫り
逢坂山まで進んできた -
27.-34.
平家でなければ人でない
かつてはそうも言い切った
平家の公達も今はただ
六波羅やかたに火を放ち
燃える炎に背を向けて
二度と帰らぬ死出の旅
都を捨てて西の海
逃げてゆくのも運命か -
35.-42.
清盛の弟で
薩摩守忠度は
数騎の供をしたがえて
淀川べりまで出たものの
闇にまぎれて都に戻り
ひそかにたずねるその先は
藤原俊成卿の
五条館に違いない
-
43.-48.
忠度は俊成の前に進み
「いくさが終わって世が静まれば
勅撰集を編むように
命じられると聞きました
わたしの一生の名誉として
一首だけでも先生に
選んでもらえば幸せです」と -
49.-51.
言って鎧のすき間から
巻物一巻取り出して
両手でささげ目に涙 -
52.-55.
俊成はそれを聞き
「その時が来たならば
必ず願いをかなえましょう」 -
56.-59.
忠度喜び「これでもう
西の海に沈んでも
野山にかばねをさらしても
一つも思い残すことはない」 -
60.-64.
西に向かって進みながら
「ゆく道はまだ遠い
雁山にかかる夕方の雲
それを見ながらもの思い」
口ずさむのを俊成は
涙ながらに見送った -
65.-66.
大津の都は荒れ果てた
しかし桜は昔のまま -
67.-73.
歌はまことにすばらしい
たとえその身は滅んでも
歌に託した武士の心は
琵琶湖の水に照りはえて
残した人のゆかしさを
いつまでも伝えるだろう